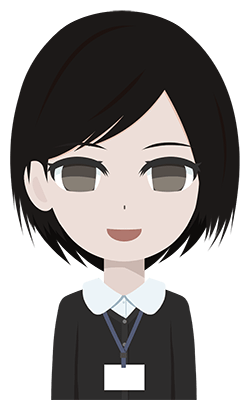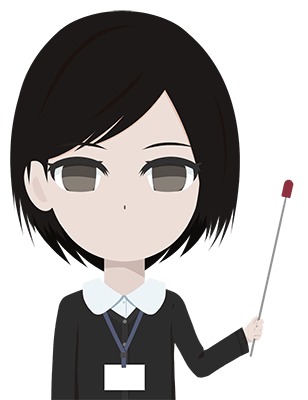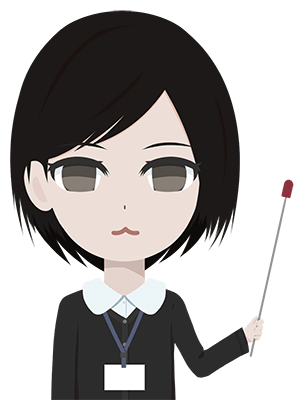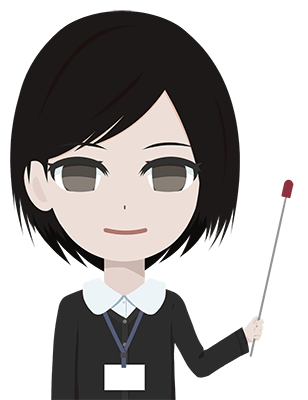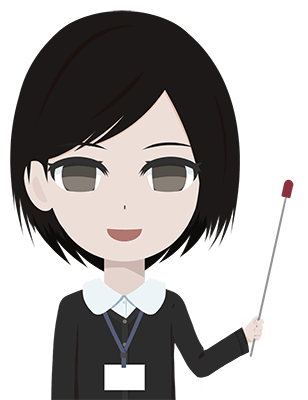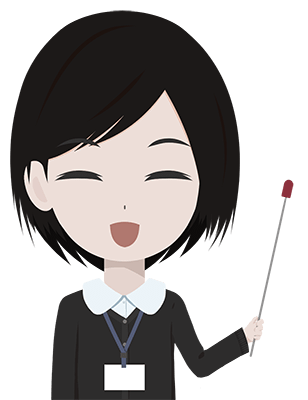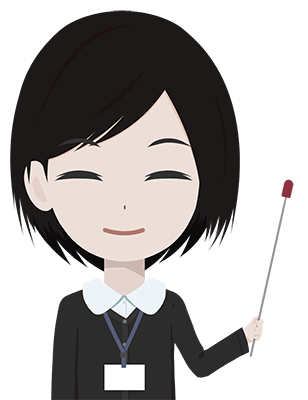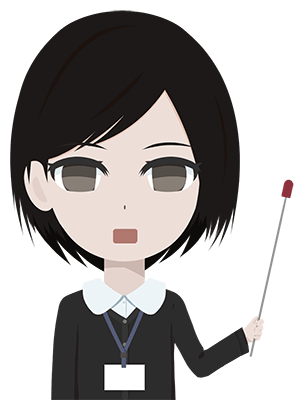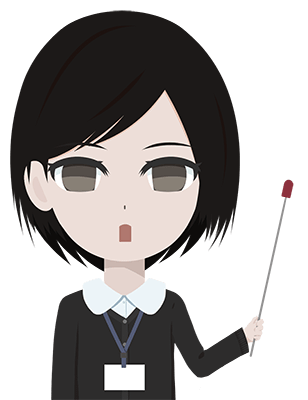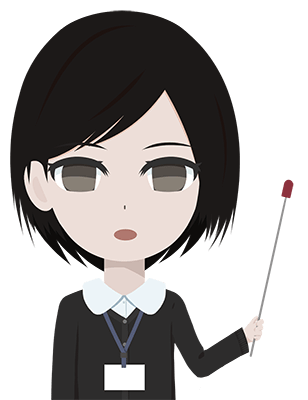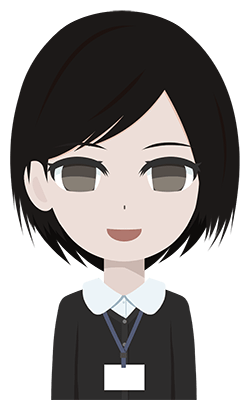
『正法眼蔵(しょうぼうげんぞう)』は、道元の主著である。
それは、道元が宋から帰国したのち晩年に至るまでの約20年間に弟子や在家の衆に示した教えを集めたもので、87巻(=75巻+12巻)にも及ぶ一大仏教思想書である。そして、古来より、「坐禅によって到達する正法の悟りの神髄が説かれている」とも、「日本の仏教思想史上屈指の名著である」ともいわれ、多くの注釈書・解説書が出されてきた。
ところが、難解をもって知られるだけあって、それら注釈書・解説書は、難しい単語を単に別の言葉に置き換えただけのものであったり、解説の方がかえって難しい言い回しになっていたりすることも少なくない。また、全体を通じて何を言いたいのかについては、さらに分かりにくく、道元の仏法をあきらかにするというよりは、一般的な道徳の実践や概念的な真理の称揚に終わってしまっていることも多い。

『正法眼蔵』の難解さの理由は、主に三つある。ひとつは、言葉が難解なことである。道元は京都の貴族の名門の生まれで、学問の素養はそこで培われたといわれる。仏教書を著すうえで当時の常識であった漢文体ではなく、和文体によって、しかも、漢語まじりの和文という道元独特の文体で書かれた本書は、現代の私たちにとっては決して読みやすいものではない。
二つめは、仏教の教えそのものが難解であることである。そもそも、正法眼蔵とは固有名詞ではない。もともとは、正法眼蔵涅槃妙心などといわれる仏教用語であり、中国には『正法眼蔵』という同名の書物もある。正法とは釈尊の教えのことで、道元は、釈尊が説いたといわれる教えをそのままの形で人びとに伝えることを眼目に、『正法眼蔵』を著したのである。道元の思想は難しい、という前に、釈尊の教えである仏法そのものの理解が私たちにとっては難しい、というのが正しい。
三つめは、最終的にズバリ何を語りかけられているのかが分かりにくい、ということである。『正法眼蔵』を読み進めるうえで、一語あるいは一分節ごとに把握できた意味は正しいと思えても、つなぎ合わせて全体を把握しようとしたとたんに、結局、道元が何を説いているのか全く意味がわからない、と感じることがよくある。解説書によって幾通りもの異なる解釈がなされている事実は、難解な仏教用語と道元によって選び抜かれた漢語が入り混じった極めて特殊な和文体による独特の言い回しが、専門家にとっても決してやさしいものではないということを示している。
『現成公案(げんじょうこうあん)』巻は、道元33歳のときの著作で、のちに『正法眼蔵』としてまとめられたときに、道元みずからの意思によって、75巻本の劈頭におかれた。なお、それよりも先に、一連の著作のまず最初に著され衆に示された『摩訶般若波羅密(まかはんにゃはらみつ)』巻は、75巻本では、『現成公案』巻に続く第二巻とされている。
それでは、『正法眼蔵』の首巻とされた『現成公案』巻には、いったい何が書かれているのか。例えば、以下は、『正法眼蔵』を訳された先生方が釈されている ”現成公案” の語の意味である。
[水野弥穂子, 正法眼蔵(一), 1990](p.53)
現実はあるがままで何不足ない真実であり、万物は分を守って平等であること
[石井恭二, 正法眼蔵現代文訳1, 2004](p.15)
諸々の存在や現象は実体がないのであるが、しかし諸々の形相として保持されている
[ひろさちや, [新訳]正法眼蔵, 2013](p.26-27)
"現成"という語は、「いま目の前に現れ、成っている存在」といった意味です。(中略)世界はいまあるがまま、そのままの存在です。わたしたちが世界をあるがままに認識できたとき、わたしたちは仏教者になれたのであり、それがすなわち悟りなんだ、と道元は言っています。
[木村清孝, 『正法眼蔵』全巻解読, 2015](p.31)
ありのままに現れている真実の様相を解き明かすとともに、その真実がおのずから自分にあらわになる、すなわち、「さとる」とはどういうことかを開示しようとしている。
これらに共通する考え方は、「この世界の在り方をありのままに了解する」という立場である。そしてこの立場は、現実に目の前に存在するものがそのまま真実だとする考え方を根拠にしている。確かに、現成公案という語は、現成している現実がそのまま真であるということを意味するといえなくもない。しかし、その真ということの意味の核心が、上述の先生方の文章には殆ど説かれていない。単純に、「目の前に見えている世界こそが真実である」というだけなら、わざわざ難解な現成公案を読むまでもなく、はじめから我々はそう信じている。そうではなくて、現成している姿がそのまま真であるとはすなわち、大乗仏教の根本思想としての「空」であり「無自性」であることにほかならない。
『正法眼蔵』を読み解く鍵は、まさに「正法」にある。道元がいう「正法」とは、釈尊の入滅以来、歴代の祖師によって嫡嫡相承されてきた正伝の仏法のことである。そしてその根本は、道元が75巻に及ぶ『正法眼蔵』の最初に書き下ろした『摩訶般若波羅密』巻の文中に示されている「諸法皆空」の理をおいてほかにはない。続いて書かれた『現成公案』巻において、「諸法の仏法なる時節・・・」と筆を進めたとき、その仏法とは『摩訶般若波羅密』巻を承けて「諸法皆空」を意味すると考える以外、ない。
『現成公案』巻の冒頭の句、「仏法なる時節」「われにあらざる時節」「豊倹より跳出」は、それぞれ、「仏法なる(空の)時節」「われにあらざる(無我の)時節」「豊倹(世俗の二項対立)より跳出」という意味であり、いずれも空の理にほかならない。迷悟「あり」も「なし」もまた、ともに空の理におけるそれである。
かくして、「現成」とは、我々が日常的な経験的世界において認識しているところの「ありのまま」を意味しているのではなく、そこから「跳出」した姿、あくまで空の理における「ありのまま」を意味していることがわかる。
それでは、空の理における「ありのまま」とは、いかなるものか。
以下、『現成公案』巻を現代語訳していく過程で、順を追って示していきたい。
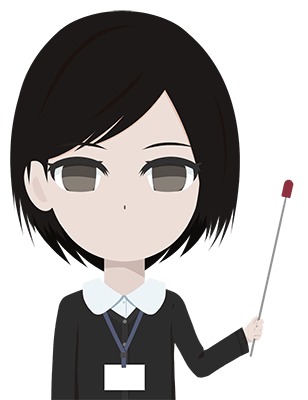
〈原文〉
1.諸法の仏法なる時節、すなはち迷悟〔めいご〕あり、修行あり、生〔しょう〕あり死あり、諸仏あり、衆生〔しゅじょう〕あり。
2.万法〔ばんぽう〕ともにわれにあらざる時節、まどひなくさとりなく、諸仏なく衆生なく、生なく滅なし。
3.仏道もとより豊倹〔ほうけん〕より跳出〔ちょうしゅつ〕せるゆゑに、生滅〔しょうめつ〕あり、迷悟あり、生仏〔しょうぶつ〕あり。
4.しかもかくのごとくなりといへども、花は愛惜〔あいじゃく〕にちり、草は棄嫌〔きけん〕におふるのみなり。
〈現代語訳〉
1.諸法(=この世界の事物の在り方)がみな仏法である(との立場に立つ)とき、迷悟があり、修行があり、生があり死があり、諸仏があり、衆生がある。(迷悟も、修行も、生も死も、諸仏も、衆生も、諸法はすべて仏法のはたらきによるものである。)
2.万法(=すべての諸法)がともにそれ自身のなかに存在根拠をもたない(との立場に立つ)とき、まどいがなくさとりがなく、諸仏がなく衆生がなく、生がなく滅がない。(まどいもさとりも、諸仏も衆生も、生も死も、すべての諸法は無我である。)
3.仏道とはそもそもあらゆる世俗的な常軌から離れたものであるがゆえに、生滅があり、迷悟があり、生仏がある。(生・滅も、迷・悟も、衆生・仏も、いずれか一方が独立して存在しているわけではなく、また、単なる世俗的な二項対立で理解できるものでもない。)
4.しかもこのようであるとはいえ、花は(人から)愛惜されながら散り、草は(人から)嫌われながら生えるばかりである。(仏法の観点からみたこの世界の事物の在り方がこのようであるとはいえ、人間が感得できる範囲は常に有限である。)
〈解説〉
"諸法"とは、岩波仏教辞典によれば、「すべての存在要素、また、あらゆる存在、事物」を表す語で、ここでは、この世界の事物の在り方というほどの意味である。また、"仏法"とは、同じく、「仏陀が発見した真理、仏陀が説いた教え」のことである。これらを合わせて、"諸法の仏法なる時節"とは、この世界の事物の在り方があまねく仏陀の説いた教えによって成り立っているとする立場に立てば、というほどの意味である。
以下は、"諸法の仏法なる時節"が「諸法は仏法である(と断定したうえで)、そのとき」なのか、「諸法が仏法であるとして(そのように受け止めたうえで)、そのとき」なのか、解釈する上でよく参照される句である。
『正法眼蔵随聞記』 [水野弥穂子, 正法眼蔵随聞記, 1992](p.258)
諸法皆仏法なりと体達しつる上は、悪は決定悪にて仏祖の道に遠ざかり、善は決定善にて仏道の縁となる。(諸法はすべて仏法であると身に親しく受け止めた上は、悪はどこまでも悪であって仏祖の道に遠ざかり、善はどこまでも善であって仏道の縁となる。)
また、"われにあらざる"とは、常住(生滅・変化なく、永久に常に存在すること)に相対立する語であるから、単純に、"われにあらざる"とは「常住ではない」ことを意味し、"万法ともにわれにあらざる"とは、すべての諸法がともに常住ではない、つまり、変化しない実体(=自性)をもたないことを示している。
"われにあらざる"に関しては、この『現成公案』巻の後段に、"万法のわれにあらぬ道理"という句が表れるが、意味は同じである。
人、舟にのりてゆくに、
a. めをめぐらして岸をみれば、きしのうつるとあやまる。
(眼をこらして岸を見れば、まるで岸が移りゆくかに誤って見える)
b. 目をしたしく舟につくれば、ふねのすすむをしるがごとく
(眼線を近づけ舟に目を落とせば、舟がすすむのがわかる)
c. 身心を乱想して万法を辧肯するには、自心自性は常住なるかとあやまる。
(五感をあれこれ働かせて万法を理解しようとすると、事物の本性には変化しない実体が存在するという錯覚に陥る)
d. もし行李をしたしくして箇裏に帰すれば、万法のわれにあらぬ道理あきらけし。
(もし仏祖先徳の足跡に従って仏法本来の境位に至れば、万法において変化しない実体はどこにも存在しない道理はあきらかである)
人が舟に乗っていくとき、a. 岸が動いていると見誤りがちだが、現実は、b. 舟が進んでいることを知る。同様に、c. 万法に自性があり常住なるかと誤りがちだが、仏法においては、d. 万法に自性はなく変化しない実体が存在しない道理はあきらかである。
"豊倹"の豊は「ゆたかさ」で倹は「まずしい」こと。つまり、貧富・貴賎・智愚など、二項対立する世間の基準。"豊倹より跳出"するとは、このような俗世間の常軌を超えていること。
『現成公案』巻には、人間の認識の限界や一面性を示した言い回しが多く現れる。「めをめぐらして岸をみれば、きしのうつるとあやまる」「ただわがまなこのおよぶところ、しばらくまろにみゆるのみなり」「のこりの海徳山徳おほくきはまりなく、よもの世界あることをしるべし」「しらるるきはのしるからざるは」などである。
諸法が仏法であるなら、仏法は、悟れるものにも迷えるものにも、虫にも花にも、山にも川にもそのはたらきを表し、道を開いているはずである。しかし、そのはたらきを会得して仏道を歩むのか、それともそれを拒絶して俗塵のなかで生きていくかは、等しくこちら側の問題である。
道元が『現成公案』巻を記したのは、決して、事物の存在の在り方を単に解明することが目的であったのではない。現成公案とは、人間の在り方とは無関係に現前している仕組みとしての法を説いているのではなく、有限な人間の認識行為の只中にあって、その中で仏道を実現しようとする動的なプロセスを説いたものである。
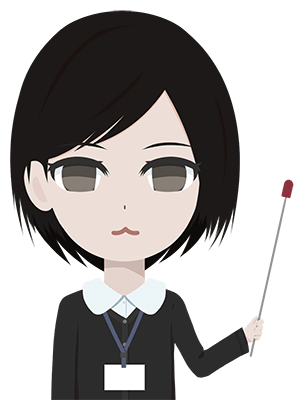
〈原文〉
5. 自己をはこびて万法を修証〔しゅしょう〕するを迷〔まよい〕とす、万法すすみて自己を修証するはさとりなり。
6. 迷を大悟〔だいご〕するは諸仏なり、悟に大迷〔だいめい〕なるは衆生なり。さらに悟上に得悟する漢あり。迷中〔めいちゅう〕又迷〔ゆうめい〕の漢あり。
7. 諸仏のまさしく諸仏なるときは、自己は諸仏なりと覚知することをもちゐず。しかあれども証仏〔しょうぶつ〕なり、仏を証しもてゆく。
8. 身心〔しんじん〕を挙〔こ〕して色〔しき〕を見取し、身心を挙〔こ〕して声〔しょう〕を聴取するに、したしく会取〔えしゅ〕すれども、かがみに影をやどすがごとくにあらず。水と月とのごとくにあらず。一方を証するときは一方はくらし。
〈現代語訳〉
5. 自己を万法に近づけるべく修行しこれを実証しようとする行為を迷いとし、万法のはたらきによって自己の在り方をあきらかにするのがさとりである。(悟りを対象化してこれを求める修行は迷いである。そうではなくて、仏法のはたらきに従って、自己の無我なるをあきらかにすることが悟りである。)
6. 迷(と悟の二項対立)を超えて大悟するのが諸仏であり、悟に(執着して)大迷するのが衆生である。更には、悟った上に悟る者もいる。迷った上に迷う者もいる。
7. 諸仏がまさしく諸仏となるときは、自己は諸仏なりと覚り知ることを必要としない。そうであっても(=自覚するしないにかかわりなく)、証(=さと)りを得た仏なのであり、仏であることを実証(=仏道修行)し続けるのである。(仏の自覚がさとりなのではない。仏道の修行と諸仏のさとりは一体であり、仏道を修し続けることでさとりを実証するのである。)
8. (しかも仏道の世界はこのようであるとはいえ、)身心を尽くして物を見る、身心を尽くして声を聞く、そのように(自己の思惟によって懸命に)会得しようとしても、鏡に映る影のようにはいかず、水に映る月のようにもいかない。一方に注目すると一方はおろそかになる。(実際は、影を見ようとすると鏡は見えない、月を見ようとすると水は見えない。諸法には人間の認識の及ばない側面があり、人間は自己の生命活動を通じて事物と出会う範囲でしか会得できない。)
〈解説〉
「自己は諸仏なりと覚知することをもちゐず」とは、一切衆生が本来的に仏でありそれを自覚することこそが悟りであると説く当時の日本仏教界を踏まえて、道元がこれをやんわりと否定している箇所である。これに関しては、『宝慶記』に道元が祖師如浄に拝問している記載があり、以下はその解説文からの抜粋である。
『宝慶記』 [大谷哲夫, 道元「宝慶記」全訳注, 2017](p.51)
道元の時代、悟りの概念として日本でも中国でも常識的な範疇で考えられていた「魚が水を飲んで、みずからその冷たい暖かいということを知るように、みずから知るのが悟りである」とする考え方が一方に存在していたのであり、それを道元は誤りであるとして「みずから知るのが悟りであるならば、一切衆生はみな、みずから知る能力をもっているから悟りを得た仏ということになるが、それが仏法と言えるのか」と拝問したのである。それに対して、如浄は「一切衆生が、本来仏というのであれば、それは自然外道である」と、そのような考えを明確に否定したのである。(略)仏法は見聞覚知のみによって得られるものではなく、この場合も自己即仏と理解することで得られるものではなく、それは信及修証によって初めて得られることを示誨しているのである。
前段の解説でも述べたように、現成公案が仏法と人間の認識行為との動的な相互作用を説示しているのだとすれば、"身心を挙して色を見取し、身心を挙して声を聴取するに、したしく会取すれども"の箇所は、『現成公案』巻の後段に出てくる以下の句を参照することで、より深く理解できる。
塵中格外、おほく様子を帯せりといへども、参学眼力のおよぶばかりを見取会取するなり。(世間から見ても出家の立場から見ても、この世界はさまざまな様相をなしているが、結局は、修行者が学んだだけの力量の範囲内で、認識したり理解したりする以外にない。)
また、"一方を証するときは一方はくらし"における"一方"は、同じく後段に出てくる以下の句の「ひとかた」に対応し、これも、いまだ人間の認識が不足している状況を表している。
身心に法いまだ参飽せざるには、法すでにたれりとおぼゆ。法もし身心に充足すれば、
ひとかたはたらずとおぼゆるなり。(いまだ修行者の身心にまで仏法が学び取られていないうちは、仏法は既に十分だとして自己満足してしまう。仏法がもし身心に充足すれば、どこかまだ不足しているように思われる。)
正法眼蔵の『山水経』巻において、さらに、以下の句を見ることができる。
『山水経』 [増谷文雄, 正法眼蔵全訳注(二), 2004](p.31)
いわゆる、水をみるに瓔珞(=ようらく/首飾り)とみるものあり。しかあれども、瓔珞を水とみるにはあらず。われらがなにとみるかたちを、かれが水とするらん。かれが瓔珞は、われ水とみる。水を妙華とみるあり。しかあれど、花を水ともちゐるにあらず。鬼はみずをもて猛火とみる、膿血とみる、龍魚は宮殿とみる、楼台とみる。あるいは七宝摩尼珠とみる、あるいは樹林牆壁とみる、あるいは清浄解脱の法性とみる、あるいは真実人体とみる、あるいは身相心相とみる、人間これを水とみる。殺活の因縁なり。
(たとえば、水を瓔珞と見るものもある。だが、瓔珞が水であるとするのではない。わたしどもがああと思いこうと見るところを、彼らは水と見るのであり、彼らが瓔珞と見るところを、わたしどもは水と見るのである。また、水を妙なる花と見るものもある。だが、花を水とするわけではない。鬼は水をもって、猛火となし、血うみと見るという。龍魚は水を宮殿と見、楼台と見るという。あるいは水をもって七宝・珠玉と見、あるいは樹林・牆壁と見、あるいは清浄なる法性と見、あるいは人間の真実体と見、あるいは身のすがた・心の本性と見るものもある。それを人間は水と見るのである。そこに殺活の鍵がある。)
以上を考え合わせれば、"一方を証するときは、一方はくらし"とは、人間の認識、さらには、人間に限らず、生きとし生けるすべての生命にとって、その殺活の行為に応じて感得される事実とその限界を述べたものであると思われる。
水はその本性において水であるのではなく、人間がその生活において見取・会取する行為において水は水に見えるのであり、龍魚がその生活において見取・会取する行為においては、水は水ではなく宮殿となる。変わらないのは水の本性ではなく、人間や龍魚の側の見取・会取する行為である。
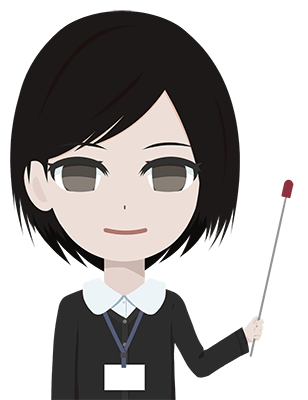
〈原文〉
9. 仏道をならふといふは、自己をならふ也。自己をならふというは、自己をわするるなり。自己をわするるといふは、万法に証せらるるなり。万法に証せらるるといふは、自己の身心および他己の身心をして脱落せしむるなり。悟迹〔ごしゃく〕の休歇〔きゅうけつ〕なるあり。休歇なる悟迹を長々出〔ちょうちょうしゅつ〕ならしむ。
10. 人はじめて法をもとむるとき、はるかに法の辺際〔へんざい〕を離却〔りきゃく〕せり。法すでにおのれに正伝するとき、すみやかに本分〔ほんぶん〕人〔にん〕なり。
11. 人、舟にのりてゆくに、めをめぐらして岸をみれば、きしのうつるとあやまる。目をしたしく舟につくれば、ふねのすすむをしるがごとく、身心を乱想して万法を辧肯〔はんけん〕するには、自心自性は常住なるかとあやまる。もし行李〔あんり〕をしたしくして箇裏〔こり〕に帰すれば、万法のわれにあらぬ道理あきらけし。
〈現代語訳〉
9. 仏道を修めるとは、自己を修めることである。自己を修めるとは、自己の無我なるを知ることである。自己の無我なるを知ることは、万法(のはたらき)に拠って(無我が)実証されることである。万法(のはたらき)に拠って(無我が)実証されるとは、自己の身心および他己(=自己以外のすべて)の身心をして(吾我を実体視する見解から)脱落させることである。(その境位においては、)悟りの跡形(=実体視されたことば等による幻想)は休みきっている(=はたらくことなく安住している)。休みきっている悟りの跡形を、すぐれたものであるとするのである。
10. 人が(仏道修行を)始めて、仏法を求めるとき、仏法の辺際(=はしっこ)からもはるかに遠く離れてしまっている。(人はもとより仏法の中にあり、人が仏法を求める道理はありえない。かといって、人は諸法のすべてを認識できるわけでもない。)仏法が身についたときには、(そのような、)本分をわきまえた人となるのである。
11. 人が舟に乗るとき、眼をこらして岸を見れば、まるで岸が移りゆくかに誤って見える。眼線を近づけ舟に目を落とせば、舟がすすむのがわかる(人は、自分の外の世界が生滅変化していることは理解できても、自分自身もその道理の例外でないことはなかなか理解できない)。それと同じように、あれこれと知覚を働かせてものの在り方を考えていると、わが心、わが本性には変化しない実体が存在するという錯覚に陥る。もし仏祖先徳の足跡に従って仏法本来の境位に至れば、変化しない自己などはどこにも存在しない道理はあきらかである。
〈解説〉
身心脱落とは、道元の悟りそのものである。それがどれほどのものであるか、以下、参考に記す。
『宝慶記』 [大谷哲夫, 道元「宝慶記」全訳注, 2017](p.106)
堂頭和尚示して云く。
「参禅は身心脱落なり。焼香・礼拝・念仏・修懺・看経を用いず、祇管打座のみ」
拝門す。
「身心脱落とは如何」
堂頭和尚示して云く。
「身心脱落とは坐禅なり。祇管に坐禅する時、五欲を離れ、五蓋を除くなり」。
(師である)如浄が(道元に)示して云われた。「参禅は身心脱落である。焼香・礼拝・念仏・修懺・看経ではない。只管打座こそが身心脱落である。」これに対し(道元が)拝問した。「身心脱落とはどのようなことなのですか。」如浄は示して云われた。「身心脱落とは坐禅そのものである。祇管(=ただ)、坐禅するとき、人間のもっている五つの欲望から離れ、五蓋から除かれるのである。」
『同』(p.298)
道元は「心塵脱落」ではなく「身心脱落」といわれたからこそ、「身心脱落とはどういうことか」と拝問したのである。人間の欲望や煩悩を心に積もる塵とし、それを修行によって洗い流し、清浄な心を得るのを「心塵脱落」というが、「只管打座」が単に「心塵脱落」のようなことであるならば、道元があえてそれを質問するはずがない。只管打座の真髄が「身心脱落」であると示されたので、その真意を拝問したのである。
『同』(p.297)
如浄下での弁道において、道元が最も感銘を受けたのが「身心脱落」の示誨である。如浄は学人を接得する際、幾度も「身心脱落」のことばを用いていたようであるが、道元はこれを如浄における仏法の真意と確信した。帰国の後、道元は自己の禅風を挙揚する上で、「身心脱落」を根幹に据えた。だからこそ、『正法眼蔵』や『永平広録』においてその行実が盛んに説示されるのである。
"修"と"証"は、道元の禅思想を最も特徴づける最重要語である。
『辨道話』 [水野弥穂子, 正法眼蔵(一), 1990](p.28)
それ修証はひとつにあらずとおもへる、すなわち外道の見なり。仏法には、修証これ一等なり。いまも証上の修なるゆゑに、初心の辨道すなわち本証の全体なり。かるがゆゑに、修行の用心をさづくるにも、修のほかに証をまつおもひなかれとをしふ、直指の本証なるがゆゑなるべし。すでに修の証なれば、証にきはなく、証の修なるは、修にはじめなし。
道元は、禅の修業を「修」、さとりを「証」と呼び、修と証とは相即不離の関係にあるとする。一切衆生は仏性であるが、しかし、その仏性は修行しなければ現成することはなく、しかも、これを実証しなければ我が身に正法を確信し会得することはできない。つまり、修行の実践こそが仏法の正しさを証することであり、修と証とはひとつ(=修証一等)である。そして、さとりを自覚し顕現するものが坐禅である。道元にとって、坐禅はさとりの手段ではなく、只管打座、坐禅そのものがさとりなのである。
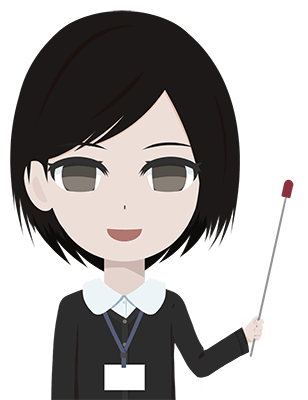
〈原文〉
12. たき木、はひとなる。さらにかへりてたき木となるべきにあらず。しかあるを、灰はのち、薪はさきと見取すべからず。しるべし、薪は薪の法位に住して、さきあり、のちあり。前後ありといへども、前後際断せり。灰は灰の法位にありて、のちありさきあり。
13. かのたき木、はひとなりぬるのち、さらに薪とならざるがごとく、人のしぬるのち、さらに生とならず。しかあるを、生の死になるといはざるは、仏法のさだまれるならひなり。このゆゑに不生といふ。死の生にならざる、法輪のさだまれる仏転なり。このゆゑに不滅といふ。
14. 生も一時のくらゐなり。死も一時のくらゐなり。たとへば、冬と春のごとし。冬の春となるとおもはず、春の夏となるといはぬなり。
〈現代語訳〉
12. 薪は灰となる。さらに戻って灰が薪になることはできない。それなのに、灰はのち、薪はさきとみなすべきではない。知るべきである、薪は、薪とみなす在り方(=ことばのはたらき)を受けて先があり後がある。前後があるといっても、その前後は断ち切れている。灰は、灰とみなす在り方(=ことばのはたらき)を受けて後があり先がある。("薪が灰になった"というとき、そこに薪はない。すなわち、ここで薪ということばが意味しているのは、今ここにある具体的な事物ではなく、それは、過去・現在・未来を超越して該当する概念上の薪である。このようなことばのはたらきを根拠とすることではじめて、先があり後がある、といえるのである。)
13. その薪が灰となった後にもう一度薪にはならないのと同じように、人が死んだ後、さらに戻って生となることはない。そういうことであるので、生が死になると言わないのは、仏法の昔からの考え方である。("甲が乙になる"という認識の仕方をしないのが仏法である。そもそも、甲と乙が時間を超越して該当する本質のごとき根拠を設定しない限り、"甲が乙になる"という言い方は原理的に成り立たない。これを成り立たせているのが、ことばが仮設する概念の世界である。ところが、この本質のごとき根拠は、あくまでことばの機能が生み出した錯覚であり、実際にはどこにも存在しない、というのが仏法の立場である。)これゆえに不生という。(一般に"甲が死ぬ"というとき、それが死ぬ前であればまだそれは生きているので、甲が生きている以上は"死ぬ"とはいえない。もしそれが死んだ後であれば、甲はすでに存在しておらず、存在していないものが改めて"死ぬ"ことはありえない。つまり、死すべきいかなる生も存在しないから、これゆえに不生という。)死が生にならないというのも、同じように仏法の昔からの考え方である。これゆえに不滅という。(死んだものは生き返らない、ということを問題にしているのではない。仏法の立場では、生となるべきいかなる死も存在しないから、これゆえに不滅という。)
14. 生はその時のものの在り方にすぎず、死はその時のものの在り方にすぎない。(生も死も、いかなる本質も実体ももってはいない。)例えば、冬や春のごとくである。冬が春に変化したわけでも、春が夏に変化したわけでもない。(ただ冬の状態があり、ただ春の状態があるだけである。決して、何らかの変化しない実体が存在してその実体が冬から春へと姿かたちを変貌させた、というわけではない。)
〈解説〉
我々が日常的に暮らしているこの経験的世界には、種々さまざまな事物が存在しており、それらは、ひとつひとつの名称をもっている。きまったひとつの名称をもつということは、きまったひとつの本質をもつということである。より正確にいえば、きまったひとつの「本質」をもっているかのように見える、ということである。
薪は「薪」という名称をもち、かつ、薪が薪たる本質をもつ。
灰は「灰」という名称をもち、かつ、灰が灰たる本質をもつ。
薪と聞けば薪の本質のイメージが喚起され、灰と聞けば灰の本質のイメージが喚起される。さらには、薪は燃えて灰となる概念上の先後関係が呼び起こされる。
これが、通常、我々が了解している現実の経験的世界である。
何の区別も境界も名称も定められていない原初の現実世界の全体から、ある一部分を括りだして意識を集中させ、一個の独立した存在として見立てる。この部分的な存在物の中核をなし、そのモノをそのモノたらしめている固有性が、「本質」である。その「本質」がことばによって名指しされることで、一定の事物として我々の意識に現成する。
通常、我々は、このようなプロセスをいちいち意識することなく、既に割り当てられた名称とその本質の組み合わせを学習することで、経験的世界を生きている。
ところが、大乗仏教は、このような、ことばによって様々に分節された経験的世界を妄念の世界と呼び、ことばによって名指しされるいかなる本質も認めない。
『八千頌般若経』[梶山雄一. (2001). 大乗仏典2八千頌般若経Ⅰ. 中公文庫.](p.26)
世尊よ、幻と感覚は別々のものではなく、表象も、意欲も別なものではありません。感覚、表象、意欲こそが、世尊よ、幻であり、幻こそが感覚、表象、意欲なのです。
『中論』[中村元. (2002). 龍樹. 講談社学術文庫.](p.364)
心の境地が滅したときに、言語の対象もなくなる。真理は不生不滅であり、実にニルヴァーナのごとくである。
『空七十論』[梶山雄一. (2004). 大乗仏典14龍樹論集. 中公文庫.](p.97)
名称であらわされる事物(法)はすべて涅槃と同じく実体(自性)が空であるから。
ことばは、それと一致する対象を実在の世界にもつわけではない。本質とは、実は妄念の描き出す虚構であって、すべては空なるものにすぎない、というわけである。
さらにいえば、大乗仏教のいう平等とは、Xなるものも、Yなるものも、そもそもすべてがことばの分節機能によって仮設された妄想上の概念にすぎず、はじめからいかなる区別も存在しない(=畢竟平等)、XとYは区別できない、ということである。
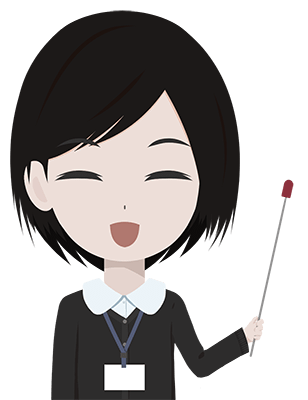
〈原文〉
15. 人のさとりをうる、水の月のやどるがごとし。月ぬれず、水やぶれず。ひろくおほきなるひかりにてあれど、尺寸の水にやどり、全月も弥天(みてん)も、くさの露にもやどり、一滴の水にもやどる。
16. さとりの人をやぶらざる事、月の水をうがたざるがごとし。人のさとりを罣礙〔けいげ〕せざること、滴露の天月を罣礙せざるがごとし。ふかきことはたかき分量なるべし。時節の長短は、大水〔だいすい〕少水〔しょうすい〕を検点し、天月の広狭〔こうきょう〕を辨取〔はんしゅ〕すべし。
〈現代語訳〉
15. 人がさとりを得るということは、水に月が映るようなものである。(月が水に映っても)月が濡れることはなく、(水に月が映っても)水が割れることはない。月は広く大きな光ではあるが、小さな水溜りにも映り、月全体も天全体であっても、草の露にも映り、一滴の水にも映る。(水を人とし月をさとりとするならば、さとりがどれほど広大無辺であっても、すべての人に教えは開かれており、いかなる者も、仏道を修めることでさとりを得ることができる。)
16. さとりが人を損なうことがないのは、月が(水に映っても)水に穴を開けることはないようなものである。人がさとりの妨げにならないことは、ほんの僅かな水であっても(水であれば)天や月を映すのに何の妨げにもならないようなものである。水の深さ(さとりの深さ)は、そのまま天の高さのごとくである。さとりに至る年月の長短については、水の大小によって映る天月の広狭に違いがないことをしらべたうえで、自身で弁(=わきま)えるべきである。(水の大小でそこに映る天月の広狭に違いはなく、自身の修行の深い浅いは自身で反省するがよい。)
〈解説〉
ここでも、大乗仏教の徹底した平等観が説かれる。以下は、その要約である。
貴賎・男女・利鈍・智愚にかかわりなく、どんな人間でもさとりを得ることが出来るのは、広大無辺の月の光が、どんな小さな水溜りにも草露にも一滴の水にも宿るがごとくである。
また、さとりを得たからといって人が特別の何者かに変わるわけではないのは、月が水面に映ったとしても、月の光が水に穴を開けることがないし、水が月の大きさで破れるということがないのと同じである。
しかも、さとりに至る年月の長短やさとりの深浅が人によって異ならないのは、水の大小によってそこに映る天月の広狭に違いがないのと同じである。
しかあれば、その違いを決めるのは、仏道修行の深浅以外にないことを、自身でよくよく弁えるべきである。
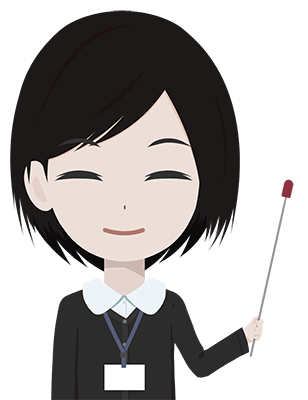
〈原文〉
17. 身心〔しんじん〕に法いまだ参飽〔さんぽう〕せざるには、法すでにたれりとおぼゆ。法もし身心に充足すれば、ひとかたはたらずとおぼゆるなり。たとえば、船にのりて山なき海中にいでて四方(よも)をみるに、ただまろにのみみゆ、さらにことなる相みゆることなし。しかあれど、この大海、まろなるにあらず、方(けた)なるにあらず。のこれる海徳つくすべからざるなり。
18. 宮殿〔ぐうでん〕のごとし、瓔珞〔ようらく〕のごとし。ただわがまなこのおよぶところ、しばらくまろにみゆるのみなり。
19. かれがごとく、万法もまたしかあり。塵中〔じんちゅう〕格外〔らくがい〕、おほく様子を帯せりといへども、参学眼力のおよぶばかりを見取会取〔えしゅ〕するなり。万法の家風をきかんには、方円とみるよりほかに、のこりの海徳山徳おほくきはまりなく、よもの世界あることをしるべし。かたはらのみかくのごとくあるにあらず、直下も一滴もしかあるとしるべし。
〈現代語訳〉
17. いまだ修行者の身心にまで仏法が学び取られていないうちは、仏法は既に十分だとして自己満足してしまう。仏法がもし身心に充足すれば、どこかまだ不足しているように思われる。例えば、舟に乗って陸の見えない先まで海に出て四方を眺めると、ただ円いばかりで、それ以外の異なる形には見えない。しかし、この大海は、海そのものとして円いわけではなく、四角いわけでもない。残る海のさまが見えていないだけである。
18. 龍であれば水を自分の宮殿と見て、天人はこれを宝石の髪飾りと見るという。ただ、人が自身の感覚器官を通じて認識する形として、大海を見れば円く見るというだけのことである。(海がもとから海という変わらぬ本質をもって存在しているわけではなく、認識する主体によって、宮殿であったり、髪飾りであったり、円くみえたりするということである。)
19. このたとえは、万物すべての事物の在り方にあてはまる。世間から見ても出家の立場から見ても、この世界はさまざまな様相をなしているが、結局は、修行者が学んだだけの力量の範囲内で、認識したり理解したりする以外にない。この世界の事物の在り方を仏法にしたがい学ぼうとするならば、円や四角に見える以外にも、残る海の見え方や山の見え方は無限にあり、さらには、自分の見える範囲を超えて、四方に世界が広がっていることを知らねばならない。しかも、まわりの世界だけではなく、自分自身も、もっと小さな世界でも、またそのようにあると知らねばならない。
〈解説〉
再び人間の認識の限界について言及したうえで、ついには、龍や天女の認識にまで及ぶ。人が舟から大海を見ると海が円く見えるのは、人の視点から隠れた残る海の全体が見えないからにすぎない。一方、同じ水であっても、龍は宮殿と見て、天女は首飾りと見る。
ここで道元が強調していることは、事物に「本質」を見て名称を割り当てる仕方は、本来限りなく自由であるということである。我々人間が、人間独自の感覚器官に触発されて、人間の殺活にかかわる効用にしたがい、人間としての文化的な価値観の制約を受けて行う名称の割り当ては、無限に可能な「本質」特定のうちのひとつの仕方であるにすぎない。
それがいかに偏狭で、独善的で、一方的なものであるかは、いま仮に龍となり天女となって、我々人間が通常、水と決め込んで疑いもしないものに対して、龍や天女の視点から、名称を新たに割り当てようと考えてみればすぐにわかる。
さらに詳しい説明が、『山水経』巻にあるので抜粋する。
『山水経』 [増谷文雄, 正法眼蔵全訳注(二), 2004](p.35)
いま人間には、海のこころ、江のこころをふかく水と知見せりといへども、竜魚等いかなるものをもて、水と知見し、水と使用すといまだしらず。おろかにわが水とともがら、水をならはんとき、ひとすぢに人間のみにはとどこほるべからず。すすみて仏道のみづを参学すべし。仏祖のもちゐるところの水は、われらこれをなにとか所見すると参学すべきなり。仏祖の屋裏、また水ありやなしやと参学すべきなり。
(いま人間は、海のこころ、河のこころと、ふかく水を知っているようであるが、なお、龍魚などはどういうものを水と見、水と思っているかはまだ知らない。自分が水と思っているものを、いずれの類のものも水として用いているであろうと思ってはならぬ。いま仏教をまなぶ人々は、水を考える場合にも、ひたぶるに人間の立場に固執してはならない。すすんで仏教の水の考え方を学ぶがよい。仏祖がもちいるところの水を、自分はどう考えているのか。また、仏祖の家においては、水があるかないか。そのようなことをまなびいたるがよろしい。)
実のところ、我々が、その存在をその存在たらしめている根拠としてもとから備わっていると思っているモノの本質なるものは、人間がその効用に基づいて妄想した虚構の産物にすぎないのである。
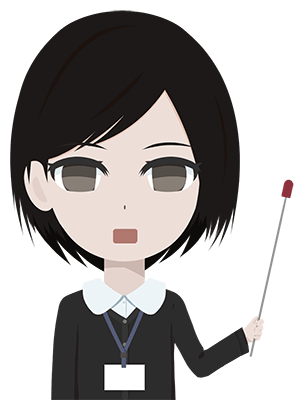
〈原文〉
20. うを水をゆくに、ゆけども水のきはなく、鳥そらをとぶに、とぶといへどもそらのきはなし。しかあれども、うをとり、いまだむかしよりみずそらをはなれず。只用大のときは使大なり。要小のときは使小なり。
21. かくのごとくして、頭々に辺際をつくさずといふ事なく、処々に踏翻せずといふことなしといへども、鳥もしそらをいづればたちまちに死す、魚もし水をいづればたちまちに死す。
22. 以水為命しりぬべし。以空為命しりぬべし。以鳥為命あり、以魚為命あり。以命為鳥なるべし。以命為魚なるべし。このほかにさらに進歩あるべし。修証あり。その寿者命者あること、かくのごとし。
〈現代語訳〉
20. 魚が水を泳ぐとき、どこまで泳いでも水に終わりがなく、鳥が空を飛ぶとき、どこまで飛んでも空に終わりがない。だがいまだかつて、魚は水から離れたことはなく、鳥は空から出たことはない。ただ、(魚や鳥は)大きく動くときは(水や空を)大きく使い、小さく動くときは小さく使う。(水や空は、魚や鳥と無関係に独立してもとから存在しているわけではなく、魚が水のなかを泳ぐことで水が水として存在し、鳥が空を飛ぶことで空が空として存在する。)
21. このようにして、それぞれに魚が限りを尽くして水を行き、鳥がところとして飛ばないところがない。ところがもし、鳥が空を出ればたちまち死に、魚が水を出ればたちまちに死ぬ。(魚自身も水によって魚としてあり、鳥自身も空によって鳥としてある。)
22. (この世界の事物のあり方を仏法の観点から洞察すれば、)水を以って命と為し、空を以って命と為すと、知るべきである。鳥を以って命と為し、魚を以って命と為す。また、命を以って鳥と為す、命を以って魚と為す、というべきかもしれない。このほかさらに続けることも出来る。まさにここに修証あり。その命あるものの在り方とは、このようなものである。(自己と修行とさとりの関係は、鳥と空と命の関係と同じく、三者は一体である。)
〈解説〉
魚と水の関係や、鳥と空の関係は、修行者と仏法の関係の喩えである。
以魚為命、以水為命、以命為魚、以鳥為命・・・。魚と水と命、鳥と空と命について、それぞれ主客を入れ替えた命題が3度ずつ繰り返される。このほかさらに続けることも出来るといい、すべては相互に依存する関係性の中でのみ存在し、いかようにも主題の転換が可能であることが示される。
仏法の立場では、それぞれが固有の実体をもつ独立した存在ではなく、すべては縁起で成り立ち、相互に依存しながら存在している。つまり、魚は水中を泳ぐ行為によって魚として存在し、鳥は空中を飛ぶ行為によって鳥として存在している。そして、泳ぐ行為や飛ぶ行為によって、魚や鳥の命が実証される。修行者もまた、仏法の只中を修行する行為によって修行者としてある。そして、修行する行為によってさとりが実証されるのである。
かくして、「修行」と「証り」は一体となる。
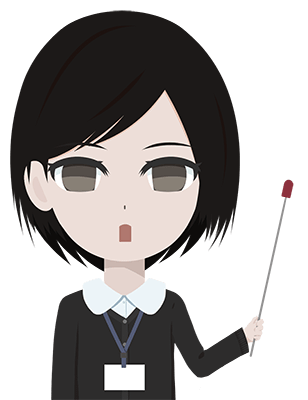
〈原文〉
23. しかあるを、水をきはめ、そらをきはめてのち、水そらをゆかんと擬する鳥魚あらんは、水にもそらにもみちをうべからず、ところをうべからず。このところをうれば、この行李〔あんり〕にしたがひて現成公案す。このみちをうれば、この行李したがひて現成公案なり。
24. このみち、このところ、大にあらず小にあらず、自にあらず他にあらず、さきよりあるにあらず、いま現ずるにあらざるがゆゑにかくのごとくあるなり。
25. しかあるがごとく、人もし仏道を修証するに、得一法、通一法なり、遇一行、修一行なり。これにところあり、みち通達せるによりて、しらるるきはのしるからざるは、このしることの、仏法の究尽と同生し、同参するゆゑにしかあるなり。
26. 得処かならず自己の知見となりて、慮知にしられんずるとならふことなかれ。証究すみやかに現成すといへども、密有かならずしも現成にあらず、見成これ何必なり。
〈現代語訳〉
23. そうであるのに、水を水として(独立した本質をもつ存在として)了解し、空を空として(独立した本質をもつ存在として)了解してから、水を泳ごう、空を飛ぼう、というような魚や鳥がいるとしたら、彼らは水にも空にも、泳ぐみちを得ることはできず、飛ぶところも得ることはできないであろう。鳥が空にところを得るとしたら、飛ぶ行為において、その存在の在り方が問われなければならない。魚が水にみちを得るとしたら、泳ぐ行為において、その存在の在り方が問われなければならない。
24. (魚が泳ぐ)このみちや、(鳥が飛ぶ)このところは、大小にあらず、自他にあらず、もとからあったものでもなく、今新たに現じたものでもない、まさにこのようにあるものなのである。(仏法においては、魚が個々に泳ぐことで魚が泳ぐ「みち」が通じ、鳥が個々に飛ぶことで鳥が飛ぶ「ところ」がひらかれる。)
25. それと同じく、人がもし仏道を修める場合、一法を得てはその一法に通じ、一行に遇ってはその一行を修する(というやりかた意外にない)。これにより、仏法を証する「ところ」が開かれ、「みち」が通じるのである。修行で知られる極限が判らないのは、これを知ること自体が仏法の究め尽くされた状態と一致するからであり、これを参究すること自体が仏道であるゆえにそのようにあるのである。(仏道を生きるとは自分の足下を生きること以外にない。あくまで仏道を修する行為を通じて仏法の極限は証明されるのであり、一法一行に通じる実践の積み重ねによってのみ、仏法を証する「ところ」が開かれ「みち」が通じるのである。)
26. 修行で得たるところは、必ずしも自己の知見となって分別できると考え慣れてはいけない。さとりを極めれば即座に現成するといっても、親密なる諸法それ自体はかならずしも目に見えるようなかたちで立ち現れるものではなく、自己が見て取った(はずの)世界はかならずしもそのとおり見えるわけではない。
〈解説〉
繰り返しになるが、仏法の立場では、魚が魚として、水が水として、独立した本質を持って別個に存在しているのではない。魚はあくまで水との関係性のなかで存在し、水は魚との関係性のなかで存在する。このとき、魚と水を結び付けているのは、魚が水の中を泳ぐという行為である。これと同じように、人とさとりを結び付けるのも一法一行に通じた仏道修行以外になく、しかも、結局は、修行者が学んだだけの力量の範囲内で認識し理解する以外にない。
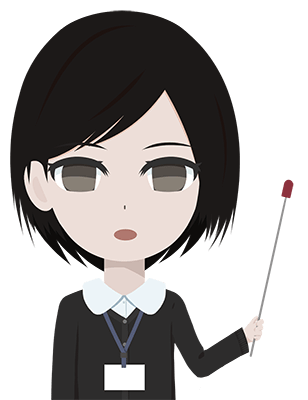
〈原文〉
27. 麻浴山〔まよくざん〕宝徹〔ほうてつ〕禅師、あふぎをつかふちなみに、僧きたりてとふ、「風性常住〔ふうしょうじょうじゅう〕、無処不周〔むしょふしゅう〕なり、なにをもてかさらに和尚あふぎをつかふ」。師いはく、「なんぢただ風性常住をしれりとも、いまだところとしていたらずといふことなき道理をしらず」と。僧いはく、「いかなるかこれ無処不周底〔むしょふしゅうち〕の道理」。ときに、師、あふぎをつかふのみなり。僧、礼拝す。
28. 仏法の証験、正伝の活路、それかくのごとし。常住なればあふぎをつかふべからず、つかはぬをりもかぜをきくべきといふは、常住をもしらず、風性をもしらぬなり。風性は常住なるがゆゑに、仏家の風は、大地の黄金なるを現成せしめ、長河の蘇酪を参熟せり。
〈現代語訳〉
27. 麻浴山の宝徹禅師が扇を使っていたときに、僧が来て問うて言った、「風性は常住(常にあり)にして、処として行きわたらない場所はないという、それなのに和尚はなぜさらに(扇を)使うのであるか」。師は言った、「あなたはただ風性は常住(常にある)ということは知っているが、まだ、処として行きわたらない場所はないという道理は分かっていない」。僧が言った、「では、処として行きわたらない場所はないというのは、どういうことでありましょうか」。その時、師はただ扇を使うのみであった。それを見て、僧は(その意味をさとり)礼拝した。(「扇ぐ行為において風が風として現れる、修行の実践においてもとから備わっていた仏性が仏性として現れる」と解釈することも可能であるが、縁起の観点では少し違う。扇ぐという行為が「"風"そのもの」なる存在を仮設させる。風とは実際に「吹く」ことであり、「"風が"吹く」「"風が"吹かない」と言うことはできない。同じように、修行によって仏性が現れるのではない、実際に修行することが「仏性がある」ということを可能にしているのである。)
28. 仏法の明らかなること、仏法に対して正しく生きることとは、このようなものである。(風は)常にあるから扇を使うべきではない、(扇を)使わずとも風はあるというのは、常住ということも知らず、風性ということも知らないのである。風性は(扇ぐ行為において)常住であるからこそ、仏道修行の風は、大地が黄金であることを顕現させ、長河の豊かな水を酪乳に熟させるのである。(仏道修行の風は、この世界の事物の在り方を根本から転換させるような仕方で吹く。つまり、この世界の全ての事物は、それ自体としてもとから存在しているわけではなく、あくまでことばによる分節機能によって仮設されたものであり、それ以外のものとの関係性の中ではじめて生成されるものである。このように仏道を修することが、即ち仏法を証することなのである。)
〈解説〉
わずか13歳で叡山に登り翌年に出家した道元が学んだ当時の天台教学は、「本来本法性(人間は本来 仏の心を持ち)天然自性心(生まれながらに仏の身体を有している)」というものであった。
しかし、もしそうであるならば、もともと悟っているものがなぜ修行をするのか。生まれながらに完成された人格を持っていながら、なぜ諸仏は苦しんでまで修行をするのか。もともと悟っているのに、なぜ悟りを求めて発心修行しなければいけないのか。その修行とはいかなるものか。若き道元は、当時の日本仏教がかかえる根本的な矛盾にいち早く気づき、悩みぬく。
本来仏であることと、修行して仏となることに根本的な矛盾があることは火を見るより明らかのはずであるが、少年僧道元が抱いた素朴な疑問は、周囲の学僧たちにとっては、出家以前のきわめて幼稚な質問にしか映らなかった。
この疑問を解決することが、道元の求道の精神に重大な意義付けをもたらし、それ自体が道元の仏法を大きく特徴付けることとなる。入宋した道元は如浄に巡り合い、如浄膝下で只管打座の弁道により身心脱落した後、帰国して修証一等の仏法を確立する。
風はどこにでも吹いているのに、和尚はなぜさらに扇を使うのか?
(誰もが仏性を持っているのに、人はなぜ修行をするのか?)
風が処としていきわたらない道理を、あなたは理解していない。
(仏性が本性としてあるわけではない事実を、あなたは理解していない。)
扇で扇ぐという行為において、風が風として現れるのである。
(仏道を修するという行為において、さとりがさとりとして実証されるのである。)
(誰もが仏性を持つとはいっても、仏としての行為をしなければ仏とはいえない。)
(修することが仏としての行為であり、仏としての行為がそのまま修すること(=証上の修)である。)
道元が『現成公案』巻の最後にこの宝徹禅師の問答をおいたのは、この問答が、若き日に自身が抱いた疑問に対する結論として道元自身が到達した修証一等の境位に、そのまま重なるからである。
そしてまさにこの境位を衆に示すことこそが、『現成公案』巻の趣意なのである。
(終)
石井恭二. (2004). 正法眼蔵現代文訳1. 河出書房新社.
石井義長. (2011). 『正法眼蔵』「現成公案」の説示について. 印度学佛教学研究第五十九巻第二号.
井筒俊彦. (1991). 意識と本質. 岩波文庫.
伊藤秀憲. (1976). 一方を証するときは一方はくらしの論理. 駒澤大学佛教学部論集第七号.
伊藤秀憲. (1982). 『正法眼蔵抄』口語訳の試み 現成公案(一). 駒澤大学佛教学部論集第十三号.
宇井白寿, 高崎直道. (1994). 大乗起信論. 岩波文庫.
大谷哲夫. (2014). 道元「永平広録 真賛・自賛・偈頌」. 講談社学術文庫.
大谷哲夫. (2017). 道元「宝慶記」全訳注. 講談社学術文庫.
鏡島元隆, 水野弥穂子. (2002). 道元禅師全集「正法眼蔵1」. 春秋社.
梶山雄一. (2001). 大乗仏典2八千頌般若経Ⅰ. 中公文庫.
梶山雄一. (2004). 大乗仏典14龍樹論集. 中公文庫.
梶山雄一. (2008). 梶山雄一著作集第四巻「中観と空Ⅰ」. 春秋社.
梶山雄一. (2012). 梶山雄一著作集第二巻「般若の思想」. 春秋社.
木村清孝. (2015). 『正法眼蔵』全巻解読. 佼成出版社.
佐藤悦成. (1992). 『正法眼蔵』「山水経」考. 印度学佛教学研究第四十巻第二号.
杉尾守. (1966). 道元禅師における現成公案の意義. 印度学佛教学研究第十五巻第一号.
辻口一郎. (2012). 正法眼蔵の思想的研究. 北樹出版.
角田泰隆. (1996). 最近の道元禅師研究. 駒澤短期大学佛教論集第二号.
角田泰隆. (2007). 『正法眼蔵』「現成公案」巻冒頭の一説の解釈. 印度学佛教学研究第五十六巻第一号.
角田泰隆. (2012). 道元入門. 角川文庫.
中村元. (2002). 龍樹. 講談社学術文庫.
橋田邦彦. (1925). 正法眼蔵釈意. 山喜房佛書林.
ひろさちや. (2013). [新訳]正法眼蔵. PHP研究所.
増谷文雄. (2004). 正法眼蔵全訳注(一). 講談社学術文庫.
増谷文雄. (2004). 正法眼蔵全訳注(二). 講談社学術文庫.
水野弥穂子. (1990). 正法眼蔵(一). 岩波文庫.
水野弥穂子. (1992). 正法眼蔵随聞記. ちくま学芸文庫.
水野弥穂子. (2002). 道元禅師全集「正法眼蔵1」. 春秋社.
南直哉. (2008). 『正法眼蔵』を読む 存在するとはどういうことか. 講談社選書メチエ.
矢島忠夫. (2010). 正法眼蔵『山水経』. 弘前大学教育学部紀要第103号.
山内舜雄. (1986). 『正法眼蔵抄』と天台本覚法門. 駒澤大学佛教学部論集第十七号.